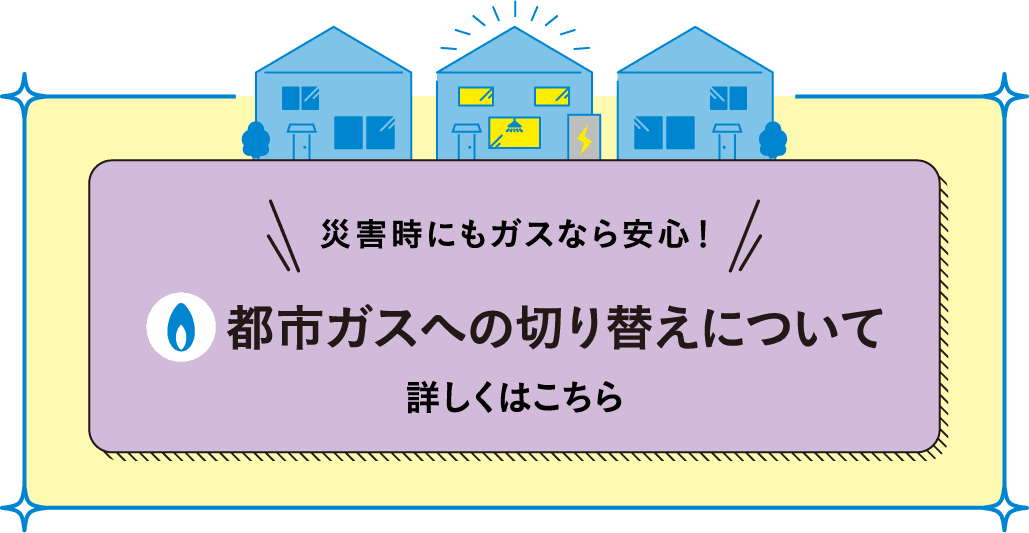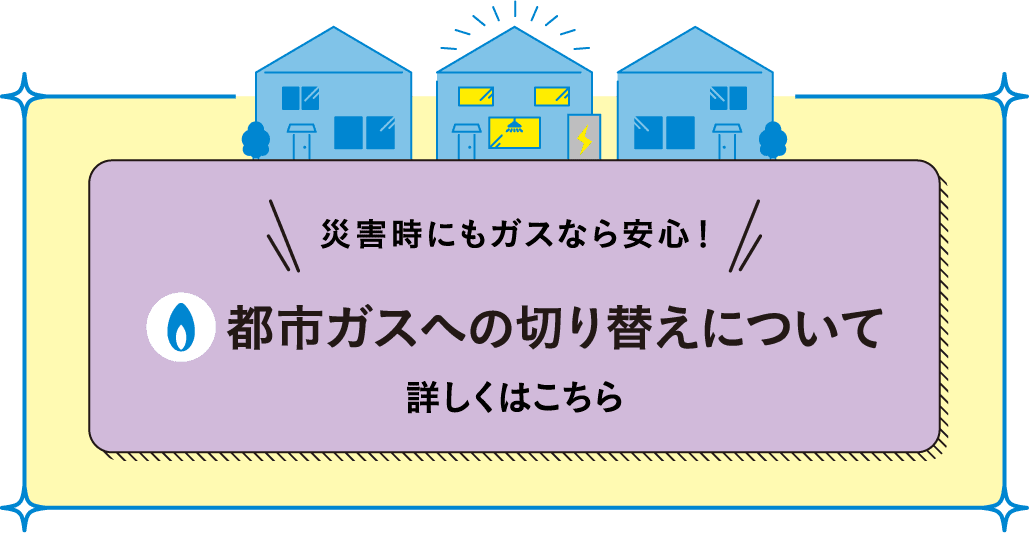自家発電の種類と特徴は?メリット・デメリットも確認!
2025.10.30 更新
電気代の節約や非常時の備えとして、家庭での自家発電が注目されています。
そこで今回は、自家発電の種類や特徴を解説!
家庭に自家発電を導入するメリット・デメリットもあわせて紹介しますので、検討されている方はぜひ参考にしてみてください。

自家発電の種類は?特徴と費用も確認!
自家発電とは、家庭や企業に発電設備を設置して自ら電力を作り出すことです。
省エネの取り組みや、災害など非常時の備えとして注目されています。
自家発電の発電方法には以下のような種類があります。
太陽光発電
建物の屋根などにソーラーパネルを設置し、太陽光が当たることで発電、パワーコンディショナーで電気に変換して使用します。
太陽光という再生可能エネルギーを用いた発電方法なのでエコですし、二酸化炭素も発生せず地球に優しいです。
太陽光パネルの設置費用は1kWあたり25万円程度といわれ、全国的な平均積載量4.5kWだと120万円程度が目安です。
風力発電
自然に吹く風で風車を回し、そのエネルギーで発電する方法。
こちらも再生可能エネルギーです。
家庭用の小型の風力発電設備は、数万円から10万円前後で購入できるものもあります。
一般的には、家庭よりも企業などで大型の設備を設置するケースが多いようです。
燃料電池
ガスから取り出した水素を空気中の酸素と化学反応させて熱を作り、発電する方法です。
ガスを燃焼させるわけではないので、発電時に二酸化炭素が少ないことが大きな特徴です。
価格はメーカーや設備によっても異なりますが、200万円程度が目安です。
エンジン式発電
ガソリンなどの燃料を燃焼させ、エンジンを動かして発電する方法です。
発電機自体は数万円~10万円程度で購入できるので、非常用の電源として重宝するでしょう。
燃料が燃焼するにおいやエンジンの駆動音が大きいため、使用の際には周囲への配慮が必要となります。
手動式発電
ハンドルやペダルを回して人力で発電する方法です。
発電量は多くないので、ラジオや懐中電灯、携帯電話の充電をするなど、緊急時の備えとするケースが多いでしょう。
蓄電池との組み合わせでさらに使いやすく
自家発電では発電しているときにしか電気を使えないので、蓄電池と組み合わせることで使い勝手が良くなります。
据え置き型蓄電池は容量が大きく、夜間や災害時にも通常と同じように電気が使えます。
一方、モバイルバッテリーやポータブル電源のような可搬型蓄電池は手軽に使える反面、蓄電容量が限られています。
また、非常時に電気自動車(EV車)を蓄電池代わりにするという考え方もありますよ。
自家発電のメリット・デメリットを解説

家庭で自家発電を利用するメリットとデメリットを、それぞれご紹介します。
【メリット1】電気代が節約できる
家庭で使用する電気を自家発電で作り出せれば、電力会社から購入する電気を減らせるので、電気代を節約できます。
太陽光発電や風力発電では、余った電力を国に買い取ってもらえるケースもあります。
【メリット2】災害時にも電気が使える
地震や台風で停電になってしまっても、自家発電や蓄電池があれば必要最低限の電気を使うことができます。
最近は全国で災害が頻発しているので、緊急時の備えとしても安心ですね。
ただし、自家発電の機器によっては、停電すると使用できないものもあるので注意が必要です。
自家発電のエネファームやコレモの停電時の機能や使用可能量の目安、注意点などは「エネファームやコレモなど自家発電は停電時に使える?注意点も解説」をご覧ください。
【デメリット1】設置やメンテナンスに費用がかかる
太陽光発電や燃料電池、蓄電池などの自家発電装置は、機器購入や設置工事などの初期費用として100万円以上の費用がかかることも珍しくありません。
また、設置後も定期的な点検や不具合の修理など、メンテナンス費用がかかります。
【デメリット2】すべての家に設置できるわけではない
太陽光発電ではソーラーパネルを設置するのに日当たりの良い屋根、燃料電池でも機器を設置するのに条件の合った広さの設置場所が必要となります。
蓄電池の設置についても同様で、住宅や敷地の条件によっては設置できないケースもあるでしょう。
自家発電の自家消費と売電とは?
自家発電で作り出した電気を家庭で消費することを「自家消費」、電力会社と契約をして買い取ってもらうことを「売電」といいます。
国は売電について10年間の固定価格買取制度を設定しており、売電契約から10年間は同じ価格で売電できます。
しかし、電気の買取価格は年々下がっていて、2021年の買取価格は19円/kWh、2022年度は17円/kWh、2023・2024年度は16円/kWh、2025年は15円/kWhに。
自家発電した電気を売却すると、副収入が得られるというメリットがあります。
自家発電の種類はどうやって選ぶ?選び方のポイント
家庭に設置する自家発電の種類を選ぶポイントとして、まずはその目的が日常的に使うものか、非常用なのかを考える必要があります。
日常的に使うためなら太陽光発電、風力発電、燃料電池で発電して、蓄電池で電力を貯めて使うという組み合わせがベター。
太陽光発電は初期費用について補助金制度を実施している自治体もあります。
災害時の非常用電源としての備えなら、エンジン式の発電機やポータブル蓄電池などが初期費用が少なく導入しやすいといえるでしょう。
家庭用燃料電池として北ガスでも「エネファーム」を提供しています。
天然ガスから取り出した水素と酸素を化学反応して発電し、発電時の排熱でお湯を沸かして給湯にも活用するシステムです。
「停電しても電気が使える」「断水しても生活用水が使える」「ガスが止まってもお湯が使える」と、電気・⽔道・ガスのいずれかが⽌まっても対応できますので、災害時も安心です!
さらに、ガスボイラーのエコジョーズと組み合わせて使うガスコージェネレーションシステムの「コレモ」もおすすめ!
こちらはガスエンジンで発電し、排熱をエコジョーズの給湯と暖房に使う仕組みです。
冬の停電時でもお湯や暖房、非常用コンセントが使えますので、北海道の災害時にもしっかり備えることができます。
住居の環境やライフスタイルに合わせて検討してみてくださいね。
まとめ
●自家発電とは、家庭や企業に発電設備を設置して電気を作り出すこと。
省エネ対策や災害への備えとしても注目されています。
太陽光発電、風力発電、燃料電池、エンジン式発電、手動式発電などの種類があり、蓄電池と組み合わせることでさらに使い勝手がアップします。
●自家発電は電気代が節約できること、災害などで停電したときにも電気が使えることがメリット。
しかし、設置やメンテナンスに費用がかかるのがデメリットで、住宅の条件によってはすべての家に設置できるとは限りません。
●太陽光発電は電力会社と売電契約をすることで余った電力を買い取ってもらえるので、副収入になります。
しかし電力の買取価格は年々下がっています。
●自家発電の種類は、日常的に使うためのものと非常用のものに二分されます。
日常的な自家発電装置は、太陽光発電や燃料電池と蓄電池の組み合わせがベター。
北ガスでも、家庭用燃料電池のエネファームや、ガスコージェネレーションシステムのコレモをご提案していますよ。
光熱費の削減やエネルギー源の変更を考えている方は、ぜひ都市ガスへの切り替えも検討してみてはいかがでしょうか。
おトクになった事例もぜひご覧ください!